第1章 「国産2ナノ」試作成功の舞台裏──再起をかけた現場のリアル
驚きのスピード感で進んだ開発プロセス
北海道・千歳にあるラピダスの工場が本格稼働を開始したのは2025年4月のこと。そのわずか3か月後、7月10日には、回路線幅2ナノメートル(nm)のトランジスタ動作確認に成功し、業界関係者の注目を集めました。
このスピード感は異例とも言われており、18日には直径30センチメートルの黄金色のウエハーをメディアや顧客候補に向けて披露。年末にはトランジスタの特性改善を終え、顧客向けにPDK(プロセス・デザイン・キット)の最新版を提供する予定とされています。
📝用語解説:2ナノメートル(nm)
1nm=10億分の1メートル。トランジスタの微細化が進むほど、より高性能で省電力な半導体が実現可能になります。

2nm品の動作確認まで3か月というのは、国際的に見ても非常に早い対応です。これは現場の集中度と連携力の高さを示す象徴的な成果ですね。
IBMと連携した中核技術の取得
今回の試作成功の裏には、米IBMとの緊密な技術連携があります。ラピダスは、回路設計から製造プロセスに至るまで、2ナノ半導体に必要な技術をIBMと共同で開発。中でも注目されるのが、GAA(ゲート・オール・アラウンド)と呼ばれる新しいトランジスタ構造や、電圧を極めて繊細に制御する技術、さらに微細な回路間での電流漏れを防ぐ絶縁膜の形成技術です。
ラピダスの技術者たちは、IBMの研究所に約200名規模で派遣され、その技術を千歳のラインで再現するためにノウハウを積み上げてきました。これらの技術取得にかかるライセンス料は数百億円に上るとされ、政府による公的支援がその一部を支えている形です。
📝用語解説:GAA(ゲート・オール・アラウンド)
トランジスタの中心であるチャネルを、ゲートが全周から包み込む構造。これにより、電流の漏れを抑えて性能を向上させることができます。



IBMとの連携は単なる技術導入ではなく、実質的な“共創”に近い関係。日本の技術者が米国の最前線で学び、その知を国産ラインで再現している点が非常に重要です。
歩留まり50%を超えるための執念と工夫
試作成功は大きな一歩ではありますが、本当の勝負はここから。量産に向けた最大のハードルが「歩留まりの改善」です。現在、初期段階での目標は50%。将来的には80〜90%を目指すとされています。
そのためにラピダスは、AIによる製造データの分析を駆使し、異物混入や装置調整による欠陥を可能な限り減らす取り組みを強化。現場では「ほぼ寝ない」体制での条件出しが続けられ、まさに開発と生産が一体となった集中状態が維持されています。
📝用語解説:歩留まり(良品率)
製造したウエハーのうち、規格を満たした製品の割合。採算性や顧客からの信頼に直結する、量産工程における最重要指標の一つです。



歩留まり50%という数字を軽視してはいけません。微細化が進めば進むほど、1%の改善にかかる労力は指数関数的に増します。その中で50%を安定的に達成するというのは、相当に緻密な工程管理と技術力が必要です。
第2章 2ナノ最前線を巡る国際競争とラピダスの現在地
世界の巨頭がしのぎを削る2ナノ競争
2ナノメートル世代の半導体をめぐって、世界の主要ファウンドリが次々と動き出しています。
まず注目すべきは、業界最大手のTSMC。2025年後半には台湾で2ナノの量産を開始する計画を進めており、米国アリゾナ州でも同世代の製造を視野に入れています。さらに、裏面から電力供給を行う「A16」プロセスの量産も2026年から始まる予定で、技術の進化が止まりません。
一方、韓国のサムスン電子も2025年中の2ナノ量産を計画。ただし、3ナノ世代の量産で苦戦していることもあり、その進捗には慎重な見方もあります。
そして米インテルは、18Aプロセスと呼ばれる2ナノ相当の技術を2024〜2025年にかけて投入する計画です。アリゾナやオハイオで新工場を建設中で、追い上げの構えを見せています。
📝用語解説:ロードマップ
半導体企業が公表する生産計画のこと。どの世代の技術を、いつ、どこで、どの規模で量産するかを示す指標です。



各社がほぼ同時期に2ナノへ突入するというのは、業界としても歴史的な局面。製造地分散を進めるTSMCや、米国内生産を重視するインテルなど、地政学リスクへの対応も含めた戦略の違いが見えてきます。
ウエハー生産能力に見る「規模の壁」
世界のファウンドリと比べたとき、ラピダスがまず直面するのが「生産規模の差」です。
現在、ラピダスの12インチウエハー生産能力は月産7,000枚程度。これを2027年までに2.5万〜3万枚へ引き上げる計画を立てています。とはいえ、TSMCの主力工場は月産10万枚を超える規模が想定されており、数量の面では大きな差があります。
こうした中でラピダスが選んだのは、「特注・高付加価値」へのシフト戦略。少量多品種の生産に対応しつつ、1枚ずつ高速で処理できる独自のラインを導入することで、受注から組立までの納期を他社より短縮し、競争力を高める方向性です。
📝用語解説:ウエハー(月産)
半導体の基板として使用される円盤状の素材。1か月あたりに製造可能なウエハーの枚数で、生産能力が評価されます。



量で勝てないなら質とスピードで勝負、という考え方は現実的。ラピダスのような新興勢力が生き残るためには、規模に頼らない戦略設計が必要不可欠です。
変わる世界の調達戦略──ラピダスに期待される役割
ラピダスが今、世界の半導体設計企業から注目されている背景には、もうひとつ大きな要因があります。それが「セカンドベンダー」としての価値です。
近年、米中対立の激化により、サプライチェーンのリスク分散が急務となっています。特に米国のテック企業にとって、台湾のTSMCに依存しすぎる構造は大きなリスク。そこで、ラピダスのように日本国内で生産が可能なファウンドリに対して、代替供給元としての期待が高まっているのです。
ただし、顧客企業がラピダスを選ぶかどうかは、単なる“国産だから”では決まりません。以下のような評価軸が実際の受託判断において重視されています。
- 性能:処理能力や電力効率、チップレット対応など
- 価格:特注でもコストの妥当性が確保できるか
- 供給体制:納期の正確さ、供給の安定性
- 地政学リスク:生産地の政治的安定性
- サポート:設計段階からの技術支援体制
📝用語解説:セカンドベンダー
主要な委託先がトラブルを起こした際に備え、代替供給元として契約される企業。リスクヘッジの一環として重視されます。



顧客にとっては“安心して任せられるか”が全て。スピード、品質、そして柔軟な連携姿勢が、最終的に選ばれる理由になるんです。
第3章 量産化への3つの壁──資金・顧客・品質をどう超えるか
最大の関門、3兆円超の資金調達をどう進めるか
ラピダスが2027年に2ナノ半導体の量産を始めるためには、総額で約5兆円という巨額の資金が必要とされています。すでに政府からは累計1.7兆円を超える支援が決まっていますが、残りの3兆円超をどう確保するかが大きな焦点です。
現在検討されている資金調達の選択肢は多岐にわたります。まず政府は、2025年度後半に1,000億円規模の追加出資を検討しており、情報処理推進機構(IPA)を通じた支援体制が強化されています。さらに、トヨタやNTT、ソニーなどの既存出資企業に加え、ホンダや富士通、金融機関各社からの新規出資も視野に入れられています。
将来的には、量産後の事業安定を前提として新規株式公開(IPO)による調達も検討されており、設備そのものを株式と交換する「現物出資」の案も浮上しています。
📝用語解説:現物出資
資金の代わりに、工場や装置などの資産を株式と引き換えで企業に提供する出資方法のこと。



ここまでの公的支援を“足がかり”にして、いかに民間資金を呼び込めるかがポイントです。将来の見通しを示すことで、投資家の納得を引き出せるような構造づくりが求められますね。
顧客獲得の鍵を握るPDKと評価プロセス
ラピダスが2ナノ製品の製造受託を獲得するには、顧客候補に対して設計支援の準備を整える必要があります。その中核を担うのが、PDK(プロセス・デザイン・キット)です。
ラピダスは、年度内に最新版PDKを顧客候補へ提供する予定で、これにより半導体メーカーはラピダスの技術水準を評価できるようになります。このPDKは、EDAツール(電子設計自動化ソフト)ベンダーとの連携により構築され、設計者が製品開発を進めるうえで必要となる一連の製造情報をまとめたものです。
評価を経て、2025年末には「顧客の顔が見える」状態となることをラピダス自身が目指しており、ここが量産化を判断する重要な分岐点となります。
📝用語解説:PDK(プロセス・デザイン・キット)
ファウンドリが顧客に提供する、IC設計に必要なプロセス仕様やレイアウトルールなどをまとめたツール一式。



PDKは“設計者の道具箱”のようなもの。これが精度高く提供されるほど、ラピダスの信頼性が上がります。顧客との距離感を一気に縮められる瞬間ですね。
スケールアップと歩留まり改善のリアル
試作品を安定的に供給できるようになったとしても、量産体制の構築にはさらなる工夫が求められます。現在、ラピダスの生産能力は月産7,000枚程度。これを2027年までに2.5万〜3万枚へと拡大する計画です。
最大のポイントとなるのが「歩留まり」の向上です。小池社長は、まずは歩留まり50%を目標とし、最終的には80〜90%を目指すと述べています。そのため、AIを活用した製造データの即時解析や、異物混入の徹底対策、さらにIBMから供与された技術の現場再現を通じて、品質を段階的に高めていく方針が取られています。
この品質向上が実現すれば、初めて大口顧客との量産契約が現実味を帯びてくるのです。
📝用語解説:スケールアップ
小規模での試作から、量産に向けて生産能力を段階的に拡大していくプロセスのこと。



歩留まりが一定の水準を超えない限り、どれだけ技術的に優れていても“ビジネス”にはなりません。顧客の立場に立って、信頼できる安定供給体制を示すことが大前提になります。
免責事項
本記事は、公開されている情報をもとに作成しておりますが、内容の正確性や完全性を保証するものではありません。
ご判断の際は、必ず一次情報をご自身でご確認いただくようお願いいたします。
なお、本記事の内容に基づいて発生したいかなる損害につきましても、責任を負いかねますことをあらかじめご了承ください。

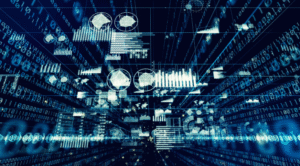
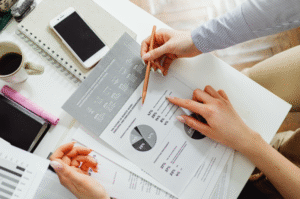
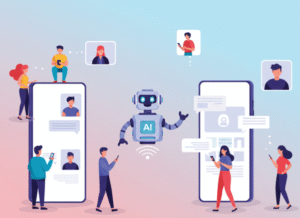


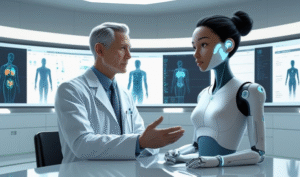
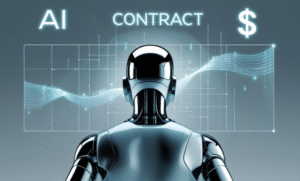

コメント