第1章 量子コンピューターの進化とRSA暗号解読リスク
1. 量子コンピューター開発、いまどこまで来ている?
ここ数年で話題にのぼることが増えてきた「量子コンピューター」。従来のコンピューターとは異なる原理で動作し、圧倒的な計算能力が期待されている次世代技術です。特に注目されているのは、その「計算の速さ」がこれまでの常識を覆すレベルにあること。開発にあたってはさまざまな方式が検討されており、たとえば超低温で動かす超電導方式や、粒子を空中に浮かせて使うイオントラップ方式、原子そのものを使う冷却原子方式など、実に多彩です。
また、冷却を必要としない光方式や、半導体技術を応用したシリコン方式、そして動作の安定性を追求するトポロジカル方式も開発の俎上にあります。これらはそれぞれ長所と課題を抱えつつ、現在も各国・各企業で活発な研究開発が進められています。
2. 実用レベルの鍵を握る“100万量子ビット”
量子コンピューターを暗号解読など実務で使えるレベルにするには、およそ100万量子ビットの規模が必要だと言われています。とはいえ、現在の到達点は100〜200量子ビットほど。そこからの飛躍を目指して、2026年には1,000量子ビット、2030年前後には1万量子ビットといったマイルストーンが各機関から示されています。
さらに、2029年を目標に100万量子ビットの到達を目指す企業もあります。補助的にスーパーコンピューターと連携させる試みもあり、量子技術単体では難しい部分を補うアプローチとして注目を集めています。
3. 最大の壁は“エラー”と“安定性”
この分野で避けて通れないのが、エラー訂正と安定動作という2つの大きな課題です。量子ビットは非常に繊細で、ちょっとした外部環境の変化で誤動作してしまうこともあります。そのため、計算中に発生するエラーをどう訂正するか、そして量子ビットをいかに安定させるかがカギになっています。
いくらビット数が多くても、計算が信頼できなければ意味がありません。この2点をクリアしなければ、どれだけ桁数を増やしても実用にはつながらないという見方もあります。
4. 暗号の“鉄壁”RSA2048も、将来は揺らぐ?
インターネットでの通信やデータのやり取りには、長年にわたってRSA暗号が使われてきました。中でも現在主流となっているのが「RSA2048」という方式で、非常に大きな桁数の素数を使うことで、解読に途方もない時間がかかるよう設計されています。実際、現在のスーパーコンピューターを使っても、解読には数万年かかると見られています。
ところが、将来的に100万量子ビット規模の量子コンピューターが実現した場合には、わずか1週間ほどで解読可能になるかもしれないという研究成果も出ています。加えて、372量子ビットでも解読可能と主張する研究もありますが、実際の処理には何百万年もかかる可能性があるとされ、信ぴょう性については慎重な見方もあるようです。
いずれにしても、「安全だと思っていた暗号が、ある日突然脆弱になるかもしれない」という未来を視野に入れておくことは、無視できない選択肢と言えるかもしれません。
5. RSA暗号の“世代交代”から学ぶこと
実はRSA暗号にも、過去に大きな世代交代がありました。かつて使われていたRSA1024から現在のRSA2048へと移行したのは、暗号技術の強化を目的としたものでした。日本国内では2008年に切り替えが周知されたものの、完全な移行には7年近くを要しました。
当時はまだインターネットが今ほど生活に根付いておらず、影響は比較的限定的でしたが、それでもメールやネットショッピング、ATMなどのサービスではシステムの更新が必要になりました。こうした実績からも、新しい暗号への移行は一朝一夕では終わらないというのが現実です。もし次の暗号更新が必要となった場合にも、余裕をもって準備を進めておくことが求められるでしょう。
第2章 耐量子計算機暗号(PQC)の技術比較と標準動向
1. 格子暗号ってなに?──次世代の有力候補
PQC(耐量子暗号)の代表格として注目を集めているのが「格子問題をもとにした暗号」です。ここでいう格子とは、空間上に点が規則正しく並んだ格子構造のこと。この構造を使った数学の難問──たとえば「最近ベクトル問題(CVP)」や「最短ベクトル問題(SVP)」といったものを基にして、安全性が成り立っています。
格子暗号のいいところは、処理に必要なのが比較的シンプルな足し算やかけ算だという点。つまり、スピーディーに暗号処理ができる仕組みなんですね。実際の運用では、安全性を保つために鍵の長さを長めに設定することがありますが、最近では鍵を短く保ちつつ安全性を維持する技術開発も進んでいて、使いやすさも向上しています。
2. エラーがカギを握る?──符号暗号の仕組み
もうひとつ、興味深いのが「符号暗号」と呼ばれる方式です。この方式の特徴はちょっとユニークで、わざとエラー(ノイズ)を計算の途中で混ぜ込むことで、安全性を高めるという仕組みになっています。
量子コンピューターは、エラーが多くなると正確な答えを出すのに時間がかかるという性質があるため、ランダムな数字を大量に含ませることで、計算を難しくする工夫がされています。以前は、暗号化に時間がかかりすぎたり、容量が大きすぎたりと実用面での課題もありましたが、最近では圧縮技術の進展によって、より現実的に使いやすいサイズに近づいてきました。
3. ハッシュ関数ベース暗号──軽くて速い新方式
「ハッシュ関数」というキーワードを聞いたことがある方も多いかもしれません。これは、特定の情報をある一定の形式に変換する技術で、一度変換されたら元に戻すのが非常に難しいという特性をもっています。これを活かしたのが、ハッシュ関数ベースの耐量子暗号です。
この方式の魅力はなんといっても処理が速いこと。暗号化や復号が比較的単純な計算で完了するため、日常的な通信などにも適していると考えられています。ただし、安全性を保つためには鍵の管理がしっかりしていることが重要。また、導入にはやや複雑な設計が必要となるケースもあり、コストや設計面のバランスが問われる部分もあるようです。
4. 世界基準を決めるNISTの動き
こうした暗号方式の標準化をリードしているのが、アメリカのNIST(国立標準技術研究所)です。NISTは2016年から新しい暗号方式の公募を始め、世界中の研究者や企業から寄せられた提案を評価。その中から、2022年7月には格子暗号ベース3方式とハッシュ関数ベース1方式が標準化されました。
さらに、2025年3月には符号問題ベースの方式も1つ追加され、現在では複数の方式を使い分ける流れが進んでいます。これは、一部の方式にもし何かしらのリスクが出ても、他の方式でカバーできるようにしておくという「多重防御」の考え方から来ています。
5. PQC導入時に気をつけたいこと
PQCを実際の業務に取り入れていくには、「どれが一番安全か?」だけでなく、処理の速さ、鍵の長さ、システム負荷なども含めて総合的に判断することが大切です。特に、金融機関やインフラ事業などセキュリティが重要な分野では、それぞれの暗号方式の特徴をきちんと見極めながら、最適な技術を選んでいく必要があります。
方式によってメリット・デメリットは異なりますが、技術が進化する中で選択肢もどんどん広がっているのが現状です。自社のシステム環境や目的に合った方式を選ぶために、基礎的な技術の違いを理解しておくことが、これからの暗号化対応の第一歩になりそうです。
第3章 日本のPQC移行ロードマップと実務課題
1. 日本政府が描くPQC移行の道筋とは
量子コンピューターの進化に伴い、日本でも次世代の暗号方式「PQC(耐量子計算機暗号)」への切り替えが検討されています。政府はすでに、内閣官房を中心に導入に向けたロードマップの作成に着手しており、2026年度には政府機関向けに具体的な移行方針を示す予定とされています。
こうした流れは、アメリカのスケジュールとも関係しています。米国では2030年末を目安にRSA暗号が非推奨となり、2035年末には現在主流の暗号が使えなくなる見通しが示されています。これを参考にしながら、日本でもタイミングを見極めつつ、段階的な対応が求められています。
2. 金融機関はどう対応する?優先度と準備の進み方
PQCの導入は、特に金融機関にとって重要なテーマになっています。理由はシンプルで、顧客情報や取引データなど、機密性の高い情報を多数扱っているからです。ただし、どの機関も一様に進んでいるわけではなく、判断基準や対応のスピードにはばらつきがあるようです。
たとえば、次のような視点から導入の優先度を検討しているケースがあります:
- どの程度の情報を暗号化して保管しているか(情報の機密性)
- サイバー攻撃のリスクや脆弱性の有無
- 移行に向けて使える人材や予算といったリソースの確保状況
- G7や周辺国の対応状況など、国際的な動向
現在は、PQC導入のためのコンサルティングや移行工程表の作成、暗号化対象データの洗い出しといった準備が少しずつ進んでいる段階にあります。ただ、すべての機関で同じように進んでいるわけではなく、現時点では検討段階にとどまる組織も少なくないようです。
3. 合意形成のむずかしさと国際連携の動き
PQC導入には技術的なこと以上に、関係者全体の合意形成がカギになるといわれています。これまでのRSA暗号の移行を見ても、一部の組織だけではなく、政府・金融当局・民間企業の足並みを揃えることが、円滑な移行には欠かせません。
現在の動きとしては、
- 内閣官房がロードマップ策定を進めており、2026年度に方針提示
- 金融庁が大手銀行や地方銀行に対し、PQC導入を働きかけ
- 専門企業によるコンサルティングで実務支援が始まっている
- G7による国際的な協調の呼びかけも強まりつつある
一方で課題も少なくありません。暗号方式の選定や導入方法がまだ確定していないこと、PQCに必要な技術者や予算の確保が難しいこと、そして中小規模の金融機関では対応が遅れがちであることなど、乗り越えるべきポイントは多くあります。
4. PQCを支える人材育成の取り組み
新しい暗号技術の普及には、それを理解し開発・運用できる人材の存在が不可欠です。日本でもすでに、いくつかの取り組みがスタートしています。
たとえば、政府の量子技術イノベーション戦略の中では、高校や大学での教育カリキュラムの充実が掲げられています。また、研究機関では学生に量子計算機を実際に使ってもらう実践的な教育も進められており、企業と連携した研修やスキル育成も活発です。
この分野で求められるスキルセットには、
- 数学をベースにした暗号技術の理解
- 量子コンピューターや通信に関する基礎知識
- 情報セキュリティやサイバー防御に関する知見
- プログラミングや設計スキル
- 非技術者への説明能力(コミュニケーション力)
などが挙げられます。多様なバックグラウンドの人材が協力しながら、次世代のセキュリティを支える体制づくりが進められている段階といえそうです。
免責事項
※本記事は、公開時点で信頼できると判断された公的情報・報道資料を基に構成されていますが、技術的・制度的な内容については将来的に変更される可能性があります。暗号技術の導入や情報セキュリティ対策に関する最終的な判断は、専門機関等にご相談のうえでご対応ください。

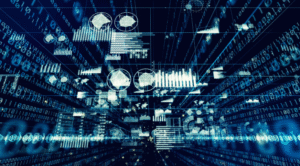
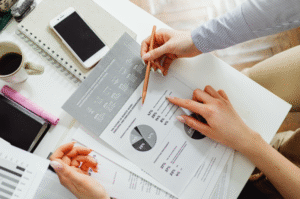
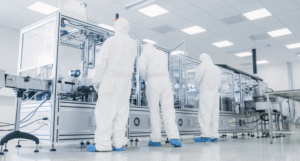
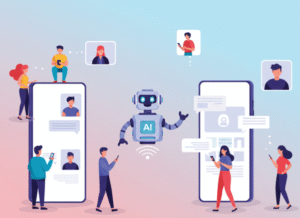

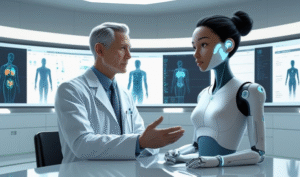
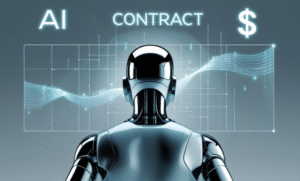

コメント