第1章 自治体システム標準化の背景と意義をわかりやすく
1‑1 制度と現場のギャップを埋めるガイドライン改定
自治体システム標準化の流れは、単なる技術対応にとどまらず、制度と現場の“ずれ”を埋める取り組みとして進んできました。
たとえば、子育て支援の手当拡充や戸籍へのフリガナ追加といった新政策が次々と実施されるなかで、各自治体とベンダーは、それぞれ個別に対応を迫られていました。その結果、業務とシステムの調整負担が膨らみ、行政全体にとっても非効率な状況が続いていたのです。
こうした状況をふまえ、2024年12月に基本方針が改定され、標準仕様書の改定ルールが「適用日の1年前までに原則改定」と明文化されました。また、移行が困難な自治体やシステムに対しては、例外的な特例措置が認められるようになっています。
さらに、ガイドライン改定では補助金制度の存続期間延長や上限額引き上げといった財政支援の強化も盛り込まれました。これは、多くの自治体から寄せられた要望を受けた対応であり、現場の声が反映された形です。

「制度変更のたびに慌てて対応していた」という声は全国の自治体に共通しています。ガイドラインの改定は、こうした負担を計画的に軽減するための第一歩なんです。
1‑2 国の構想と標準化が連動する理由
自治体システム標準化は、単体で進められているわけではありません。実は、**国の「デジタル田園都市国家構想」**と密接に連動しています。
この構想では、都市部と地方のデジタル格差をなくし、誰もが便利な行政サービスを受けられる社会の実現が目指されています。その一環として、国は「標準的な要件・機能のひな形」を公開し、自治体が迷わずに調達できるよう整備を進めています。
また、**「デジタルマーケットプレイス」**という仕組みも立ち上がりました。これは、民間の優良サービスを自治体が簡単に選べるようにする新たな調達の場で、2024年度後半から本格的に稼働する予定です。
加えて、交付金を活用した支援メニューも用意されており、標準化対応のシステム移行にかかる費用を下支えする体制が整いつつあります。



標準化は「決まりごと」ではなく、国の構想に基づく戦略的な支援パッケージの一部。言い換えると、“サポート付きの改革”なんです。
1‑3 業務のばらつきを整える仕組みとは?
かつては、同じ「転出届」の手続き一つを取っても、自治体ごとに入力画面や帳票が違うことがよくありました。これにより、制度改正のたびにシステム調整が必要になり、多くの時間とコストがかかっていたのです。
標準化はこうした状況を大きく変えます。ホワイトリスト方式が採用され、標準仕様にない機能の追加は禁止されました。これにより、自治体独自のカスタマイズが抑えられ、共通業務プロセスへの一本化が進んでいます。
もちろん、大規模な自治体ほど従来の独自機能が多く、削減に戸惑いが生じることもあるようです。しかし全体としては、業務改革(BPR)の推進や、AI・RPAの導入環境整備といった副次的なメリットも期待されています。



「業務の統一なんて本当にできるの?」と不安に感じるかもしれません。でも、少なくとも“毎回ゼロから作る”状況は確実に減っていくんです。
1‑4 住民目線で見た標準化のメリット
自治体システムの標準化は、住民サービスの質を高めることにもつながっています。
たとえば引っ越しの際、転出先と転入先の手続きが自治体ごとに異なっていたため、**住民は同じ情報を何度も書類に記入する必要がありました。**標準化によって、データ連携がしやすくなり、申請の手間やミスが減ることが見込まれています。
さらに、オンライン申請やワンストップサービスの全国展開が進めば、「引っ越したら一部の手続きが止まってしまう」といった不便も軽減されるでしょう。



「どの自治体でも同じように使える」が実現すれば、サービスの“場所格差”は大きく縮まりますね。
1‑5 海外と比べて、日本の標準化はどうなのか?
海外では、韓国が先行して地方自治体システムの統一を進めた事例があります。**「セオル行政システム」**という共通プラットフォームを2008年に全国展開し、22分野の業務を一元化しました。保守管理も中央で行い、大幅な効率化が実現したとされています。
他にも、エストニアでは「X‑Road」によって中央と地方のデータが自動連携され、デンマークでは市民サービスのデジタル化で住民満足度が向上した例があります。
こうした事例に共通するのは、**「全国統一のID設計」「共同開発によるコスト抑制」「住民利便性の徹底追求」**といったポイントです。日本では制度上すべてを中央で統一するのは難しいものの、海外の工夫は十分参考になります。



「なぜ海外ではうまくいっているのか?」という視点を持つと、日本の標準化が進む方向性もよりクリアになります。
第2章 自治体システム標準化における移行実務とベンダー対応のポイント
2‑1 標準仕様対応ベンダーの開発状況と今後の見通し
自治体システム標準化を現実のものとするには、ベンダー各社の動向を押さえることが欠かせません。
標準仕様書が2022年度末までに全20業務分公開されたのを受けて、ベンダー各社は標準仕様準拠のパッケージ開発に本格的に着手しました。住民記録や税、福祉などの分野では、2023年から順次稼働が始まっており、一部ではすでに運用が進んでいます。
たとえば、富士通Japanの住民情報システム「MICJET」は、標準仕様1.0版に対応し、全国初のガバメントクラウド上で稼働。NECも標準準拠の戸籍システムなどを展開しており、中小自治体から政令市まで対応できる製品が拡大しています。
ただし、一部の業務分野では対応製品が限定的で、ベンダーが1社しか提供していない状況も見られます。製品の機能面や納期面での不安が残る分野もあるため、状況を把握したうえで計画を立てることが求められます。
現在の見通しとしては、「2025年度内に大半の業務で稼働開始」、「一部の大型団体向けシステムは2026年度以降に対応」というスケジュールが共有されています。



「うちの業務は間に合うのかな…」と不安になるかもしれませんが、各ベンダーの対応状況を把握しておくことが第一歩です。確認すれば、次に何をすべきかが明確になります。
2‑2 RFP(提案依頼書)作成で押さえておきたい標準仕様の反映方法
標準準拠システムを導入する際、自治体が作成するRFP(提案依頼書)は非常に重要です。
ポイントは、国が定めた標準仕様書の要件を正確に落とし込むこと。RFPには「標準仕様書○○版に完全準拠したシステムであること」を明記し、必須機能と任意機能を区別する必要があります。
また、独自運用してきた業務については、Fit&Gap分析で「標準機能で対応できる部分」と「そうでない部分」をあらかじめ明確化しておくことが大切です。
さらに、RFP作成前に「情報提供依頼(RFI)」を実施し、ベンダーから提案内容を集めておくと、実際に応募してもらえる条件の整備にもつながります。
国が提供する「仕様書ひな型」や「非機能要求グレード」なども活用し、セキュリティや性能要件も含めたRFPの完成度を高めていきましょう。



「RFPに何を書けばいいかよくわからない…」という声をよく聞きます。でも安心してください。ひな型やチェックリストが整備されているので、それを参考にすればOKです。
2‑3 請負契約と準委任契約、どう使い分ける?
自治体システム標準化の導入では、契約方式の選択が成果に直結します。
請負契約は、納品物が明確で完成責任がある場合に適しており、標準仕様に準拠したシステム本体の導入にはこの方式が主に使われます。契約書には、「標準仕様準拠を保証すること」や「標準外機能の追加不可」など、具体的な条件も盛り込まれる傾向があります。
一方、準委任契約は、業務内容が流動的で成果物の定義が困難な場合に向いています。現行システムとのGap調査や移行作業の一部、帳票レイアウト調整といった作業では、柔軟性を持たせるため準委任契約が採用されています。
このように、**契約の目的や範囲によって適切な形式を選ぶことがポイントです。**また、複数契約を組み合わせる場合でも、責任の所在や契約管理の一貫性を意識する必要があります。



「どっちの契約にすればいいかわからない…」という場合でも、業務の性質(明確さや変動の有無)に注目すれば判断しやすくなります。
2‑4 セキュリティ要件のチェックリストを事前に整理する
自治体が導入するシステムには、情報漏えいやサービス停止などのリスクを最小化するため、明確なセキュリティ要件が求められます。
一般的なチェックポイントは以下のとおりです:
- 職員IDやアクセス権限など認証・認可の厳格管理
- 通信やデータの暗号化(TLSなど)
- 操作ログの記録と定期監査
- 脆弱性対策(定期セキュリティテストの実施)
- クラウド基盤の政府統一基準への適合
- バックアップと災害復旧体制の構築
また、「地方公共団体版 非機能要求グレード」やJ‑LISの「情報システムセキュリティ要求仕様モデル」など、公式ガイドをもとにチェックリストを整備することが有効です。
評価時には、ベンダーのISMS取得状況やCSIRT体制の有無など、組織体制にも目を向けておきましょう。



「セキュリティって結局どこまで見ればいいの?」と悩んだら、**まずはガイドで示されたグレードを参照してみてください。**明確な基準が設定されています。
2‑5 先行自治体が感じた“運用の変化”とは?
すでに標準化を進めた自治体では、目に見える運用負荷の軽減効果が出始めています。
たとえば、岡山県倉敷市と愛媛県松山市は共同で住民情報システムを調達・クラウド移行。ガバメントクラウド上での稼働により、サーバ管理やOS更新といった作業から解放されました。
また、東京都内のある自治体では、新しい税務システム導入により、法改正の内容が自動で反映され、担当者の作業が大幅に削減されたという声もあります。
さらに、他自治体が作成したRPAツールをそのまま活用するといったノウハウの共有もスムーズに行えるようになり、長期的な運用コスト削減にもつながっています。



「移行って本当に意味があるの?」という疑問に対しては、すでに動き出した自治体の事例が一番の答えになります。
第3章 自治体システム標準化「2025年の壁」と遅延リスクへの対応策
3‑1 自治体の標準化移行スケジュールと進捗状況
全国1,700以上の自治体が、それぞれの計画に基づきシステム標準化の移行作業を進めています。しかし、現時点ではその進捗にばらつきが見られます。
特に注目すべきは、2025年度末の移行期限までに完了予定とされるのが全体の約3割程度にとどまっているという点です。標準化対象のシステムは34,592件あり、そのうち約9.5%(3,279件)が「移行困難」とされています。
また、全国のうち約600団体が「特定移行支援システム」を抱える状態にあり、政令指定都市などの大規模団体では、すべての業務において遅延傾向が報告されています。一方、小規模自治体では、都道府県主導による共同調達が奏功し、計画通り進むケースも見受けられます。



「うちの自治体はどこに該当するんだろう…?」と思った方は、総務省の進捗状況公開ページをチェックしてみてください。業務ごとの進行度が一覧で確認できますよ。
3‑2 間に合わない自治体に見られる典型的な要因とは?
移行が遅れている自治体には、共通するいくつかの要因があります。分類すると、次の4つに整理できます。
【1】技術的なハードル
老朽化したメインフレーム上で現行システムが動いている場合、**新しい標準パッケージへの移行に時間がかかります。**クラウド対応も含めた再構築が求められるため、準備が長期化しがちです。
【2】ベンダーの対応状況
利用中のベンダーが標準準拠版を開発せず、**市場から撤退を選んだ場合、新たなベンダー選定からスタートする必要があります。**特に戸籍システムのように全国で導入シェアが高い製品では、複数の自治体が同時に影響を受けています。
【3】人員・体制の問題
全国一斉に移行が進む中で、ベンダーの開発SEや現地対応スタッフが不足しています。とくに中小規模のベンダーでは、同時に複数案件を抱えきれないという声もあるようです。
【4】自治体側の準備不足
情報政策担当の人員が限られている小規模自治体では、プロジェクト管理や調達業務が後手に回りやすい傾向があります。また、議会承認のタイミングや内部調整に時間がかかることも影響しています。



「どの要因も自分たちだけでは解決できないかも…」と不安になりますよね。でも実際は、それぞれに応じた支援策も用意されているので、早めに相談することが大切です。
3‑3 総務省の補助金と支援制度を有効活用しよう
標準化に向けた移行にはコストもかかります。そこで、総務省では**「デジタル基盤改革支援補助金」**を設け、自治体の取り組みを後押ししています。
この補助金は、標準準拠システムへの移行に伴う一時経費──たとえば、現状調査、データ移行、テスト、研修、接続設定などの費用を対象としています。
補助の対象は原則として、ガバメントクラウドへの移行が前提ですが、他のクラウドを利用する場合でも、条件を満たせば例外的に支援対象となることがあります。
補助率は自治体の規模によって異なりますが、**通常は対象経費の1/2または1/3、過疎地域などでは上乗せ措置も可能です。**また、都道府県職員による「標準化リエゾン」の派遣など、技術的な支援体制も整備されています。



「うちみたいな小規模自治体でも大丈夫?」と感じるかもしれませんが、補助の仕組みは規模に応じて柔軟に対応されているので、ぜひ確認してみましょう。
3‑4 ベンダーの人員不足にどう向き合うか
今、自治体と同じくらい課題を抱えているのがベンダー側の人材確保です。
標準仕様の開発要件が想定以上に増えたことで、**多くのIT企業でエンジニア不足が顕在化しています。**そこで、国と業界が連携して「事業者協議会」を立ち上げ、自治体と対応可能なベンダーのマッチングを行う仕組みを整備しました。
また、大手企業では社内外のリソースを活用して、クラウド対応の専門人材を育成・投入する動きも活発です。NECや日立システムズでは、研修制度を通じて地方自治体向けの支援体制を強化しています。
さらに、**必要に応じて移行期限の個別延長(最大5年)**も認められるなど、スケジュールの柔軟性も考慮されています。



「エンジニアが足りないなら進めようがないのでは?」という心配もありますが、**今は国全体でこの山場を乗り越える体制づくりが進んでいます。**焦らず、着実に。
3‑5 移行支援サービスを“味方”につけるという選択肢
移行の遅れによって生じるリスク──たとえば、法改正への対応が間に合わない、災害時の復旧体制に差が出る、住民間でのサービス格差が広がるなど、想定される事象は少なくありません。
そのため、多くの自治体では「サービス継続計画(BCP)」の中に、システム移行遅延を想定したシナリオを組み込む対応が求められています。
このようなリスクに備える手段のひとつとして、民間の「移行支援サービス」を活用する選択肢があります。
たとえば、日立システムズが提供している**「ガバメントクラウド移行支援サービス」**では、調査や構築・データ移行までを一括でサポートする体制が整えられており、リソース不足に悩む自治体にとっては心強い存在となり得ます。



「外部サービスって費用が心配…」という声もありますが、補助金制度と併用すれば、費用負担を抑えながら専門的な支援を受けることも可能です。
免責事項
本記事は公的機関等の資料に基づき執筆されていますが、実際の判断や導入方針は、必ず一次情報をご確認の上でご決定ください。
また、本記事の情報に基づいて発生したいかなる損害についても責任を負いかねますことをあらかじめご了承ください。

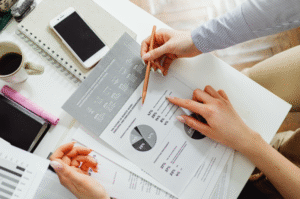
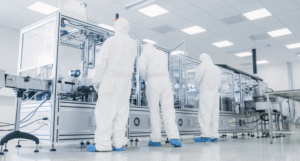
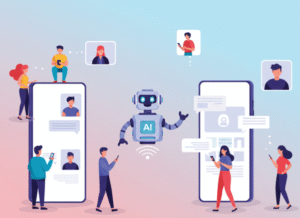


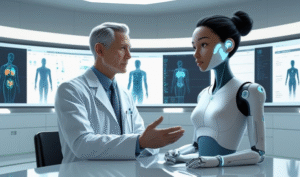
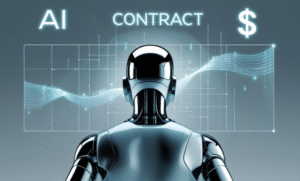

コメント