第1章 セルフ式マーケティング拡大の背景と現状
1‑1 外注から内製へ──時代が求めたマーケティングの変化
かつて「広告=代理店に任せる」が常識だった時代から、いまや多くの企業が“セルフ式”すなわちマーケティングの内製化へと舵を切っています。
実際、米国の広告主団体である全米広告主協会(ANA)の調査では、2008年に42%だった内製化率が、2023年には82%にまで上昇。15年で倍増したこの変化は、一時的な流行ではなく、企業の根幹戦略に深く根ざした動きと言えるでしょう。

「内製化率の上昇は、単なるコストの話ではありません。組織の機動力やブランドの一貫性を高めるための“必然”なのです」
この流れは日本にも確実に広がり、2025年現在、あらゆる業種の企業が“自分たちの手で動かすマーケティング”に挑みはじめています。
1‑2 企業がセルフ式を選ぶ4つの理由
内製化を進める背景には、企業にとって見逃せない4つの明確なメリットがあります。
① コスト効率の改善
広告代理店に任せると、制作費や運用費に加え、広告費の15〜20%相当の手数料がかかることも珍しくありません。これらのコストを抑えることで、マーケティング投資のパフォーマンスが改善されます。
② 透明性とデータ活用力の向上
内製化により、広告費が「どこに・どう使われているか」を社内で把握できるようになります。また、自社が持つ**ファーストパーティデータ(自社で取得した顧客情報)**を、外部に出すことなくスピーディに活用できる点も重要です。



「特に近年は“データを活かせる企業ほど強い”と言われています。内製化はその土台作りになるのです」
③ スピードと柔軟性の強化
施策の立案・修正・展開をすべて社内で完結できるため、代理店とのやり取りによる時間的ロスがなくなります。市場の変化や緊急対応にも即応できる体制が整うのです。
④ ブランド理解と一貫性の確保
社内の担当者は、自社のサービスや顧客を深く理解しているため、外部に頼るよりも一貫したブランドメッセージや世界観の維持が可能になります。
1‑3 内製化の広がりを支えた環境要因
米国でのセルフ式導入率は、**2008年に42% → 2013年に58% → 2018年に78% → 2023年には82%**と、段階的に上昇しています。
この成長を後押ししたのは、景気の影響・デジタル化・SNSの普及・広告自動化の進展など複数の要素。中でも、企業が自社データを活用しやすくなったことは、特に大きな転換点となりました。
また、ANAの調査では、「内製化による業務効率化」よりも、「ビジネス成果の最大化(売上や顧客指標)」を重視する企業が増えていることが示されています。



最近の企業は“費用を削減できるか”ではなく、“売上につながるか”で内製化を評価しはじめています
1‑4 国内事例に見る“内製化の成果”と進め方
内製化の動きは、日本でも本格化しています。
たとえば、大手家電量販店ではGoogleのAI広告ツール「P‑MAX」を導入し、広告運用の自動化に成功。人手を増やすことなく広告成果を高めています。
また、宿泊業の星野リゾートでは、SNSや予約データの分析結果をすぐに新プランや価格戦略へ反映。マーケティング施策と経営判断をリンクさせ、客室稼働率を高めています。
さらに、メルカリやリクルートも、MA(マーケティングオートメーション)ツールを使って内製化を推進。ユーザー獲得コストやIT予算を抑えながら、成果を確実に出しています。
1‑5 コスト削減と成果向上を同時に叶えるには?
大手企業などの事例では、広告費を大幅に抑えつつROIを向上させた事例が報告されています。
こうした成功には、単なるコストカットだけでなく、
- 社内ノウハウの蓄積
- データに基づく判断
- 内製ならではのスピード
といった複合的な要素が関係しています。
ただし、導入初期には人員の再配置や学習負荷によって、**一時的に成果が落ち込む“実装ディップ”**も起こりやすい点に注意が必要です。



短期ではなく、中長期で見て“価値を内製する組織”を育てる意識が求められます
第2章 生成AI・自動化ツールが加速するセルフ式マーケティング
2‑1 AIで変わる広告の“当たり前”──AI Maxが示す未来像
2025年、Googleが発表した広告AIツール「AI Max」は、マーケティングの世界に新たな衝撃を与えました。
従来の検索連動型広告は、入力されたキーワードと完全一致する広告を表示する仕組みが一般的でしたが、AI Maxは“言葉の裏にある文脈”まで読み取り、最適な広告とキャッチコピーを自動で提示してくれます。
たとえば「大家族向けの電動SUV」と検索された際、AIは単語そのものだけでなく、“安全性”や“広さ”“価格帯”といった文脈まで加味し、最適な車種とフレーズを導き出しました。しかも、こうした対応はすべて自動かつリアルタイムに行われるのです。



これはもう“広告を打つ”ではなく、“AIが広告を導く”時代に入った証拠ですね。担当者の感覚だけに頼らない、精緻な設計ができますよ
2‑2 生成AIで変わる広告クリエイティブの3つの進化
生成AIの登場により、広告制作の現場には大きな変化が起きています。中でも注目すべきは、次の3点です。
① 制作スピードの劇的な向上
以前は、コピー案やビジュアルの作成に多くの人と時間が必要でしたが、生成AIを活用すれば制作工数を大幅に圧縮できます。ある広告制作会社では、AI導入により制作効率が5倍以上になったという報告もあります。
② パーソナライズの高度化
AIは、性別・年齢・関心分野などのユーザー属性に合わせて、最適なメッセージを即座に生成可能。“誰に、どんな言葉で届けるか”を自動で最適化できるようになり、手間をかけずに1to1マーケティングが実現できます。
③ 表現の多様化と品質の安定
広告クリエイティブの世界では、“表現力”が命ともいえます。生成AIは、過去のクリエイティブや専門家のセンスを学習して、人間のアイデアを超える斬新かつ洗練されたビジュアル表現を生み出すようになりました。



生成AIの強みは、“量産”より“多様化”です。同じ商品でも、届ける相手に合わせて訴求表現を変えられるのが大きな魅力です
2‑3 AI活用で実現した、コンバージョン改善の具体例
生成AIの導入により、広告効果がどのように変わったのか──実例を見てみましょう。
国内のあるEC企業では、AIによる広告最適化により、1件あたりの獲得コスト(CPO)を削減しつつ、広告経由の購入件数が増加。広告配信のパフォーマンス(CPM)も改善し、結果として同じ広告費でも“より多くの成果”が得られるようになりました。
このような「少ない手間で、大きな成果を上げる」流れは、人手や予算の限られた企業ほど大きな恩恵を受けられる仕組みと言えます。
2‑4 導入前に押さえたい、社内体制づくりのステップ
生成AIや広告自動化ツールを活用する際は、導入効果を最大化するための社内体制整備が不可欠です。以下の4ステップを意識して、段階的に進めるのが効果的です。
ステップ①:目的とKPIの整理
まず、AI導入によって「何を達成したいのか」を明確に設定します。売上、獲得件数、リード数など、測定可能な指標を事前に定義しておきましょう。
ステップ②:データ基盤の整備
AIはデータがなければ動きません。顧客データ、行動履歴、過去の広告パフォーマンスなど、“使えるデータ”を社内で整備することが重要です。



どんなに優秀なAIでも、粗いデータでは実力を発揮できません。“整理された情報”が何よりの武器になります
ステップ③:小規模テストから開始
いきなり全面的に切り替えるのではなく、特定の商品やキャンペーンに限定して**“スモールスタート”で効果検証**を行うことで、リスクを抑えながら最適な設定を見つけていきます。
ステップ④:人材育成とガイドライン整備
AIツールを扱う担当者には、最低限の操作知識とデータリテラシーが求められます。研修やガイドラインを通じて社内の理解と運用ルールを整備することが、長期的な活用に繋がります。
生成AIや広告自動化ツールの活用は、いまや一部の先進企業だけの話ではありません。スピード・精度・効率を求めるすべての企業にとって、マーケティングの新たな選択肢となっているのです。
第3章 セルフ式×外注の“ちょうどいい関係”──マーケティング実務の最適バランスとは?
3‑1 なぜ今でも「メディアバイイング」は外注が主流なのか?
セルフ式マーケティングが広がるなかでも、**広告枠の買い付け(メディアバイイング)**については、多くの企業が外部パートナーを活用しています。
その背景には、単なる“外注慣れ”では済まされない、明確な理由があります。
- 業界動向や価格変動をリアルタイムで追う専門性
- 数百媒体にわたる複雑な交渉・調整プロセス
- 不正広告やブランド毀損リスクへの対応力
これらの作業をすべて社内でカバーするには、高度な知識・人的リソース・経験の3つが必要不可欠。特に専門スタッフが少ない企業では、外注が実務上の現実解となっています。



“内製できるから全部やる”というのは、かえって非効率なこともあります。広告業務は“任せるべき業務”と“自社で担うべき業務”を見極める力が肝心なんです
3‑2 業務負荷の増加と“現場崩壊”を防ぐ工夫
セルフ式導入によって、社内チームの業務量が急増するケースは少なくありません。たとえば以下のような運用業務が一気に降りかかってくることがあります。
- 入札調整や予算配分の管理
- クリエイティブのABテスト
- レポート作成や施策改善の会議対応
これらは細かく見えるかもしれませんが、毎日の積み重ねが現場の負担となり、慢性的なワークフローの渋滞を引き起こしてしまうことも。
そのため、多くの企業では以下のような対策を講じています。
- 運用フローの見える化(ツールによるタスク管理)
- 施策単位の役割分担(設計/実行/分析を分業)
- 自動レポート作成の仕組みづくり



“人手不足”ではなく、“整理不足”が現場を疲弊させている場合もあるんです。まずは仕組みの整理から始めるのが近道ですね
3‑3 人材不足とスキルギャップ──現場の“見えない壁”
セルフ式導入のネックとして挙がるのが、「人が足りない」「スキルが追いつかない」といった人材・知識の壁です。具体的には以下のような課題がよく聞かれます。
- 専門知識が一部の担当者に集中し、属人化が進む
- デジタル広告や分析スキルを持つ人材が社内にいない
- 学習コストが高く、人材育成の時間が足りない
このような状況を解消するには、「個人に頼らず、組織で対応できる仕組み」が不可欠です。
たとえば、
- eラーニングや動画研修の導入
- スキルの棚卸と見える化(リスキリング計画の立案)
- 社内共有ドキュメントの整備と定期見直し
など、“属人から脱却するための小さな仕組み”を積み上げていくことが効果的です。



スキルギャップって、“能力が足りない”のではなく、“学ぶ時間が確保できない”ことが原因なことも多いんです。だからこそ、制度や仕組みで支えることが重要なんですよ
3‑4 “因数分解”して考える、内製と外注の見極めポイント
では、どの業務を内製すべきで、どこまで外部に任せるべきか──その判断をするうえで有効なのが、業務の因数分解という考え方です。
これは、業務を細かく分けたうえで、
- コア領域(企画・戦略・ブランド設計など)
- 周辺領域(配信設定・調整・集計など)
のように分類し、「社内で担うべき部分」と「外注にすべき部分」を明確に分けていく方法です。
特に、限られた人員で効率的にマーケティング成果を出すには、“全体最適”の視点で判断するバランス感覚が不可欠です。



“全部をやる”か“全部を任せる”かの二択ではありません。自社の強みと課題を見極めて、賢く組み合わせるのが今の正解なんです
3‑5 生成AI時代のマーケティング組織、どうつくる?
最新のマーケティングでは、AIを起点に設計された“AIファースト”な組織が登場しています。
たとえば、広告制作や分析、CRMなどにAIを導入し、担当者が「考える業務」に集中できるような設計です。
こうした先進企業では、次のような体制整備が進められています。
- AIツール活用に関する社内ガイドラインの整備
- 全社員を対象としたAI活用研修
- 社内専用のAIエージェント開発とR&D部門の設置
加えて、外部パートナーとの適切な連携も重要です。特にAIやマーケティングツールの導入時は、セキュリティやガバナンス体制を踏まえて外部との提携を設計するケースが増えています。



“社内で完結させる”と“外部と組んで加速する”は、どちらか一方ではありません。生成AI時代こそ、内と外をうまく融合させる組織設計が鍵になります
セルフ式マーケティングの本質は、「全部自分でやること」ではありません。
何を自社で担い、どこを外部と連携するか──その“分け方”こそが競争力の源泉になる時代です。生成AIという追い風をどう生かすかは、企業ごとの体制次第。
最適なバランスを見出すことが、これからのマーケティングの新しいスタンダードになっていくでしょう。
免責事項
本記事は、公開時点の情報に基づき作成しておりますが、内容はあくまで一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の施策や意思決定を保証するものではありません。
制度やツール、サービス内容は日々変化しているため、実際の導入・運用に際しては、必ず一次情報や公式な情報源をご確認のうえ、ご自身のご判断で進めていただきますようお願いいたします。
なお、本記事の内容を利用・参考にされたことによって生じたいかなる損害に関しましても、責任を負いかねますことを予めご了承ください。
皆さまの取り組みがより良い成果につながるよう、心より応援しております。

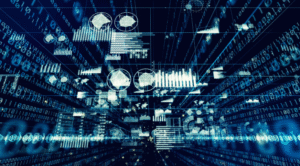
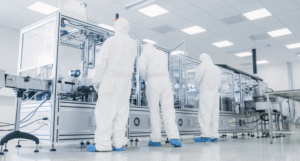
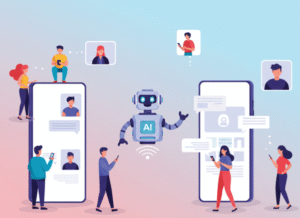


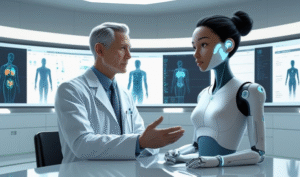
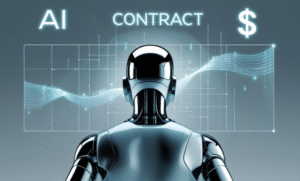

コメント